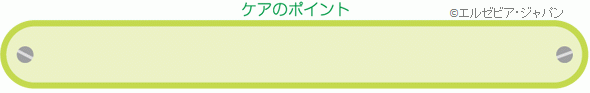
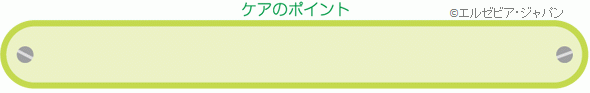
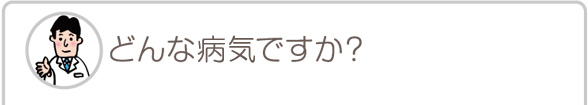
![]() 大動脈弁閉鎖不全症とは、心臓の出口にある大動脈弁という弁がきちんと閉まらないため、血液の逆流が起こり、心臓に負担がかかる病気です。
大動脈弁閉鎖不全症とは、心臓の出口にある大動脈弁という弁がきちんと閉まらないため、血液の逆流が起こり、心臓に負担がかかる病気です。
![]() 原因は大動脈弁自体にある場合と、弁周辺の大動脈基部の異常による場合があります。
原因は大動脈弁自体にある場合と、弁周辺の大動脈基部の異常による場合があります。
![]() 慢性の場合は、経過を観察しながら手術の必要性や手術時期の決定をします。急性の場合は、原因にもよりますが、緊急手術が必要な場合が多くなります。
慢性の場合は、経過を観察しながら手術の必要性や手術時期の決定をします。急性の場合は、原因にもよりますが、緊急手術が必要な場合が多くなります。
![]() 手術の必要性は、血液の逆流の程度(重症度)、心臓にかかる負担の程度(左心室機能低下や左心室拡大)、胸が痛い、動くと息切れがする、足がむくむなどの自覚症状によって判断します。
手術の必要性は、血液の逆流の程度(重症度)、心臓にかかる負担の程度(左心室機能低下や左心室拡大)、胸が痛い、動くと息切れがする、足がむくむなどの自覚症状によって判断します。
![]() 重症の大動脈弁閉鎖症でも長い間症状がでないまま経過することがあります。しかしいったん症状が出ると1年間に10人に1人以上の割で命にかかわることがあるといわれます。注意が必要です。
重症の大動脈弁閉鎖症でも長い間症状がでないまま経過することがあります。しかしいったん症状が出ると1年間に10人に1人以上の割で命にかかわることがあるといわれます。注意が必要です。
![]() 血液中に侵入した細菌が逆流のある弁について感染症を発症すると急激に悪化することがあります。
血液中に侵入した細菌が逆流のある弁について感染症を発症すると急激に悪化することがあります。
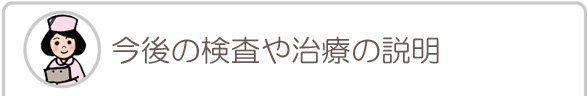
![]() 心エコー検査で、重症度を判断し、手術や経過観察期間などを判断します。他の病気との鑑別のために、運動負荷検査や胸部造影CT、心臓カテーテル検査(冠動脈造影)などを行うこともあります。
心エコー検査で、重症度を判断し、手術や経過観察期間などを判断します。他の病気との鑑別のために、運動負荷検査や胸部造影CT、心臓カテーテル検査(冠動脈造影)などを行うこともあります。
![]() 症状がある場合や、症状がなくても左心室機能障害や左心室拡大があるときは手術をします。
症状がある場合や、症状がなくても左心室機能障害や左心室拡大があるときは手術をします。
![]() 心臓の負担を減らすために薬を内服することがあります。自己判断で量を減らしたり中断したりしないようにしましょう。
心臓の負担を減らすために薬を内服することがあります。自己判断で量を減らしたり中断したりしないようにしましょう。
![]() 入院が必要な場合
入院が必要な場合
・手術が必要と診断された場合、手術には入院が必要です。 ・手術前に、心臓にかかる負担の状態を評価したり、心臓を栄養する血管(冠動脈)に狭窄や閉塞がないかを確認する(冠動脈造影)場合があり、このような場合は検査入院が必要です。
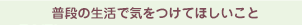 |
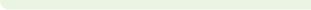 |