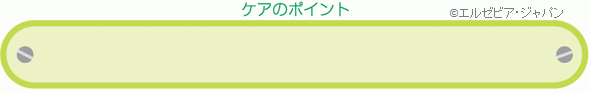
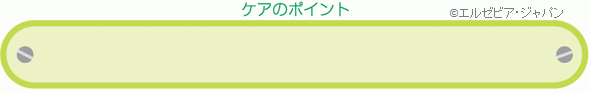
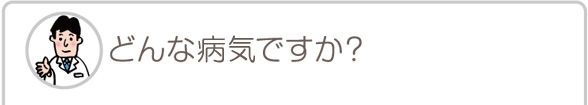
![]() 低(無)酸素・虚血後脳症は、心筋梗塞や心停止などにより、脳へ十分な酸素が送られなくなり、脳に障害が起きる病気です。
低(無)酸素・虚血後脳症は、心筋梗塞や心停止などにより、脳へ十分な酸素が送られなくなり、脳に障害が起きる病気です。
![]() 心停止後の心肺蘇生術の開始が遅れると、生存率は低下し、7分後で80%以上が死に至ります。
心停止後の心肺蘇生術の開始が遅れると、生存率は低下し、7分後で80%以上が死に至ります。
![]() 明らかに心疾患が原因の心停止で、初期心電図が心室細動で15分以内に自己心拍が再開することを心停止後症候群といいます。心停止後症候群による低(無)酸素・虚血後脳症に対する低体温療法の予後は、49~55%が良好、実施しない場合は26~39%が良好と報告されています。
明らかに心疾患が原因の心停止で、初期心電図が心室細動で15分以内に自己心拍が再開することを心停止後症候群といいます。心停止後症候群による低(無)酸素・虚血後脳症に対する低体温療法の予後は、49~55%が良好、実施しない場合は26~39%が良好と報告されています。
![]() 無酸素状態や脳虚血(脳の血液が不足する状態)、脳出血などが原因で意識障害に陥った患者さんの場合は、3カ月経ってから意識が改善するケースはほとんどありません。
無酸素状態や脳虚血(脳の血液が不足する状態)、脳出血などが原因で意識障害に陥った患者さんの場合は、3カ月経ってから意識が改善するケースはほとんどありません。
![]() 心肺停止後は、全身の酸素不足の程度や持続時間により重症度が異なりますが、約半数は24時間以内に死に至ります。
心肺停止後は、全身の酸素不足の程度や持続時間により重症度が異なりますが、約半数は24時間以内に死に至ります。
![]() 初期心電図が心静止や無脈性電気活動を示した心停止患者さんに対しての低体温療法の改善効果は7~12%程度です。心停止から12分以上たってから心肺蘇生術を開始したケースでは100%院内で死亡しています。
初期心電図が心静止や無脈性電気活動を示した心停止患者さんに対しての低体温療法の改善効果は7~12%程度です。心停止から12分以上たってから心肺蘇生術を開始したケースでは100%院内で死亡しています。
![]() 自己心拍再開まで25分以上かかった患者さんに低体温療法を行って回復した例はありません。25分以内でも、低体温療法を実施しなかった場合の回復した例は21.2%にとどまります。
自己心拍再開まで25分以上かかった患者さんに低体温療法を行って回復した例はありません。25分以内でも、低体温療法を実施しなかった場合の回復した例は21.2%にとどまります。
![]() 交通事故などの外傷が原因で重度の昏睡状態(遷延性意識障害、いわゆる植物状態)に陥った人が1年後に何らかの神経症状が改善する割合は52%、外傷以外の原因による場合は15%程度です。
交通事故などの外傷が原因で重度の昏睡状態(遷延性意識障害、いわゆる植物状態)に陥った人が1年後に何らかの神経症状が改善する割合は52%、外傷以外の原因による場合は15%程度です。

![]() 心疾患が原因による心停止は、高血圧や糖尿病、脂質代謝異常などに起因していることが多いです。これらの疾患の予防が大切です。
心疾患が原因による心停止は、高血圧や糖尿病、脂質代謝異常などに起因していることが多いです。これらの疾患の予防が大切です。
![]() 一酸化炭素中毒などの有害ガス中毒も、低(無)酸素・虚血後脳症の原因となります。心停止後や一酸化中毒による意識障害から改善しても、再び神経症状が悪化することがあります。神経症状の悪化は、回復後の数日から数週間後に始まり、遷延性意識障害に陥ることがあります。
一酸化炭素中毒などの有害ガス中毒も、低(無)酸素・虚血後脳症の原因となります。心停止後や一酸化中毒による意識障害から改善しても、再び神経症状が悪化することがあります。神経症状の悪化は、回復後の数日から数週間後に始まり、遷延性意識障害に陥ることがあります。