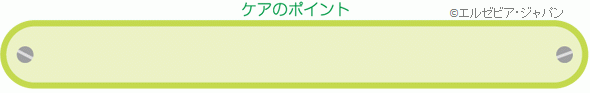
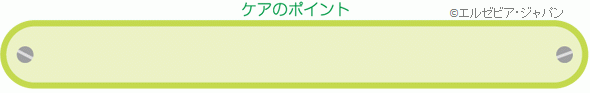
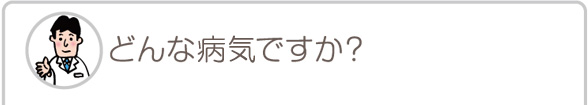
![]() 摂食障害は大きく拒食症と過食症に分けられます。若い女性の10人に1人に見られるといわれます。
摂食障害は大きく拒食症と過食症に分けられます。若い女性の10人に1人に見られるといわれます。
![]() 発症には、「やせてきれいになりたい」というファッション的な動機だけではなく、自己評価の低さや対人関係の問題、家族の問題などさまざまな因子が関係しています。
発症には、「やせてきれいになりたい」というファッション的な動機だけではなく、自己評価の低さや対人関係の問題、家族の問題などさまざまな因子が関係しています。
![]() 拒食症の場合、自分では病気と気づかず、治療の勧めに反発してしまい、低栄養が進行しがちです。低栄養が続くと、いらいらや不安が強くなり、ますます治療が難しくなるという悪循環が生じます。
拒食症の場合、自分では病気と気づかず、治療の勧めに反発してしまい、低栄養が進行しがちです。低栄養が続くと、いらいらや不安が強くなり、ますます治療が難しくなるという悪循環が生じます。
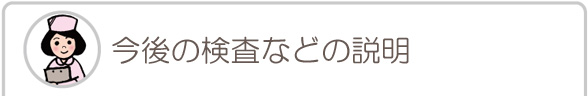
![]() 治療は、身体の状態を確認し、栄養指導や栄養剤を用いて行われます。
治療は、身体の状態を確認し、栄養指導や栄養剤を用いて行われます。
![]() 極端な低栄養状態に陥っている場合には、入院治療が必要です。また、過食嘔吐が激しく昼夜逆転になるなど生活の乱れが激しいとき、うつ状態などの精神症状が強い場合は入院となることがあります。
極端な低栄養状態に陥っている場合には、入院治療が必要です。また、過食嘔吐が激しく昼夜逆転になるなど生活の乱れが激しいとき、うつ状態などの精神症状が強い場合は入院となることがあります。
![]() 精神面に対しては、本人や家族に対するカウンセリングが行われます。
精神面に対しては、本人や家族に対するカウンセリングが行われます。
![]() 過食嘔吐症状には、抗うつ薬による薬物療法、心理療法などを組み合わせて治療が進められます。ただし、一気に症状をゼロにするのではなく、少しずつ改善させることを目指します。
過食嘔吐症状には、抗うつ薬による薬物療法、心理療法などを組み合わせて治療が進められます。ただし、一気に症状をゼロにするのではなく、少しずつ改善させることを目指します。
![]() 外来受診では、定期的に採血、検尿、心電図などの検査が行われます。体重は毎回測定します。
外来受診では、定期的に採血、検尿、心電図などの検査が行われます。体重は毎回測定します。
![]() 胃腸の働きが悪く、吸収される栄養がかなり少ない場合は、吸収のよい栄養剤が用いられます。
胃腸の働きが悪く、吸収される栄養がかなり少ない場合は、吸収のよい栄養剤が用いられます。
![]() 参考資料
参考資料
日本摂食障害協会:摂食障害患者の就労実態調査と社会復帰支援報告書.
https://www.jafed.jp/pdf/reports/working-survey.pdf
日本摂食障害協会:新型コロナウイルス感染症が摂食障害に及ぼす影響.
https://www.jafed.jp/pdf/covid-19/covid19_single.pdf
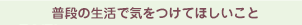 |
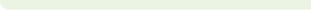 |